Interview
多様な本音が交わる共創の場で、経済と文化の融合に挑む
虎ノ門ヒルズを舞台に、クロスセクターでの社会課題解決を目指す拠点Glass Rockのオープニング企画展示「サステナビリティの本音」は、どのようにして生まれたのでしょうか。プロジェクトの背景にある想いと、共創を通じて得られた気づきについて、本企画を推進された熊田さん、倉橋さんにお話を伺いました。
話者プロフィール:熊田 ふみ子(森ビル株式会社 Glass Rock Gallery 担当)

2002年に森ビル株式会社に入社。アカデミーヒルズの企画・運営を担当する。2016年に筑波大学大学院に進学。2022年に博士(システムズ・マネジメント)を取得。2025年4月に開業した「Glass Rock」にて企画・運営に携わる。
話者プロフィール:倉橋 慶次(森ビル株式会社)

1987年森ビル株式会社入社。2003 年より「アカデミーヒルズ事業部」のカンファレンス事業責任者として「六本木アカデミーヒルズ」の営業・運営・管理業務を統括。2014 年に開業した「虎ノ門ヒルズフォーラム」の開業準備責任者として商品/サービス企画・運営体制構築等に携わる。2025年4月に開業した「Glass Rock」にて企画・運営に携わる。
サステナビリティ推進に向けた「ズレ」。誰もが関われる場とは?
Q. まず、本企画展に込めた想いや、その背景にある課題意識について教えてください。
熊田さん: 経済が行き過ぎたことによる弊害が起きているからこそ、文化と経済、その両輪を回していくことが不可欠です。以前より、都市をより強くしていくためにはアートやクリエイティブの力、すなわち “文化” が不可欠だという想いが社内にありました。経済を優先しすぎた社会のバランスを取り戻し、モノやお金だけではない、より豊かな社会を目指したい。その思想のもと、「文化と経済の融合」を体現する場として、六本木ヒルズでは森タワーの最頂部という象徴的な場所にあえて、現代美術を専門にする美術館を置きました。グローバルビジネスセンターである虎ノ門ヒルズでも、文化と経済の両輪が大事だという思想は変わっていません。その文脈の中で、「ソーシャルアクションコミュニティ」を掲げるGlass Rockは誕生しました。
倉橋さん: このGlass Rockは、多様な人が集い、共創するための拠点。私たちの理念に共感し、企業や、NPO、大学など、30を超える共創パートナーが参画してくださいました。虎ノ門は霞が関に隣接する土地柄でもあり、官僚の方々も多くいらっしゃいます。
サステナビリティを推進しよう、という大きな方向性には多くの人が「総論賛成」。ですが、それぞれ認識のプロセスや温度感にズレがあることが多々あります。私たちはそのズレを無理にまとめるのではなく、「この人はこういう考え方で動いているんだ」と互いに理解し、目線を合わせていく、そんな場にしたいと考えていました。
熊田さん: 企業の担当者の方に話を聞くと「隣の部署はコスト削減をミッションにしている中で、自分は長期的なサステナビリティを考えていて、利益にならない投資を企画していて辛い」といった声も聞こえてくる。この「建前」と「本音」が乖離したままでは、物事は前に進みません。だからこそ、まずはその本音を正直にさらけ出す場が必要だと考えたのが、この展示の原点です。来場者には、展示を見るだけでなく「私にとってのサステナビリティとは?」を自分事として考えて、この場所を後にしてほしかったのです。

Q. パートナーとして、なぜIDEAS FOR GOOD Business Design Labにお声がけいただけたのでしょうか。
熊田さん: ハーチ代表の加藤さんとの対話が大きなきっかけでした。一般的にソーシャルグッドというと、どこか「ぜいたくは敵」「苦労しながらやるべき」といった、ストイックなイメージがつきまといます。私たちが当社ならではのアプローチを模索する中で、加藤さんから「『ぜいたくは敵』という考え方では、ソーシャルグッドの広がりには限界がある。ハイエンドな価値感とソーシャルグッドを掛け合わせることこそ、森ビルらしさではないか」という、ご意見をいただいたのです。
IDEAS FOR GOODは、サステナビリティの領域で深く根を張っている専門メディアでありながら、世界の複雑な動きを初心者にも分かる言葉で伝え、知りたいと思う人のために窓口を開いてくれています。ただ「清く正しく」あるだけでなく、「ハッピーであろう」というポジティブな意志を感じられ、誰もが楽しく関われる裾野の広さがあるIDEAS FOR GOODは、今回の企画に不可欠な存在だと思いました。
1000人のリアルな「本音」、多様な思いが積み重なる場へ
Q. 弊社とのプロジェクトを通じて生まれた、最も印象的な成果について教えてください。
熊田さん: 会場に設置した、来場者が本音を書き込むステッカーボードの反響数が、想像をはるかに超えていました。最初は集まらなかったらどうしよう..自分で毎日貼りに行こうか、とまで思っていたくらいなのに、結果ステッカーが3度も品切れになり、1,000枚近いコメントが集まったんです。
コメントの中には「昇進したい」や「彼氏が欲しい」といった、一見企画の趣旨とは関係ないものもありました。社内からは「剥がした方がいいのでは?」という声もありましたが、私たちはそれらを残すことに決めました。「サステナビリティより、彼氏が欲しい」。それもまた、否定されるべきではないリアルな感情ですから。誰かを攻撃するものでない限り、すべてが個人の「本音」として、大切にしようと。この判断ができたことで、あの場は多様な想いが有機的に積み重なっていく、見ていて非常におもしろい空間になりました。
また、展示する国内外の事例をIDEAS FOR GOODさんと一緒に選んたプロセスも、非常に有意義でした。私たちが「これがいいね」と無邪気に選んだものに対し、さらに関連する別の事例を提案してくださり、その切り口や視点の定め方に多くの学びがありました。結果的に、展示で紹介させていただいた企業の皆様にも喜んでいただけたようで、この企画が誰かの貢献に繋がったという実感は、大きな喜びです。
訪れた人の「未来を考えるきっかけ」に
Q. 今回の取り組みを踏まえ、今後の展望についてお聞かせください。
熊田さん: Glass Rock Galleryを、単なる展示スペースではなく、訪れた人が「未来を考えるきっかけ」を得られる場にしていきたいです。ふと時間が空いた時に立ち寄ったら、新しい発見や気づきがあるような、インタラクティブな場所に。なぜならば、会員制の拠点ではありますが、Glass Rockの活動は常に社会に開かれているべきだと考えているからです。
これからも一方的に情報を与えるのではなく、訪れた人々との対話を通じて、一緒に未来を考えていく。そんな共創の輪を、Glass Rock Galleryから広げていきたいと思っています。

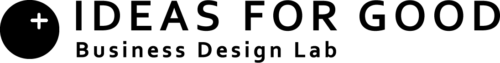










Leave your comment